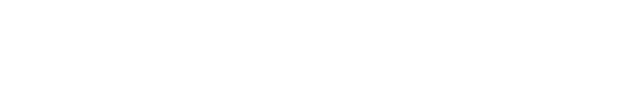ピロリ菌
ピロリ菌とは
ピロリ菌(正式名称:ヘリコバクター・ピロリ)は、胃の粘膜にすみつく細菌の一種です。らせん状の形をしており、ウレアーゼという酵素を作り出すことで胃酸を中和し、強い酸性環境の中でも生き延びることができます。
世界的に広く感染が見られる菌ですが、日本では特に中高年層の感染率が高く、かつては40歳以上の半数近くが感染しているとされていました。近年は生活環境や衛生状態の改善により若年層の感染は減ってきていますが、依然として胃の病気と深く関わる重要な菌です。
ピロリ菌の原因・感染経路
ピロリ菌は主に 幼少期 に感染し、そのまま長期間胃の中に住み着くと考えられています。
感染経路
- 井戸水など衛生状態が十分でない水の摂取
- 家族内感染(食べ物の口移しなど)
- 幼少期の生活環境の影響
一度感染すると自然に治ることは少なく、除菌治療を行わない限り胃にとどまり続けます。
ピロリ菌による症状・関連疾患
ピロリ菌に感染していても、必ずしも自覚症状が出るわけではありません。多くは無症状ですが、長期的には胃の粘膜にダメージを与え、以下の病気につながります。
- 慢性胃炎(胃の粘膜に炎症が続く)
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍(胃酸と菌の作用で粘膜が傷つき潰瘍になる)
- 胃がん(感染を放置すると発症リスクが高まる)
- 胃MALTリンパ腫(胃の粘膜にできる悪性リンパ腫の一種)
ピロリ菌の検査方法
感染の有無を調べるために、以下の検査が行われます。
尿素呼気試験
息を使って菌の有無を調べる、負担が少なく精度の高い検査です。
便中ヘリコバクター・ピロリ抗原検査
便を調べる方法で、感染の有無を判定できます。
血中ヘリコバクター・ピロリ抗体検査(血液検査)
血液中の抗体を調べる方法ですが、過去の感染との区別が難しいことがあります。
内視鏡による検査(迅速ウレアーゼ試験・組織鏡検法・培養法)
胃カメラで粘膜を観察し、組織を採取して菌の有無を調べる方法です。胃炎や潰瘍の確認も同時に行えます。
ピロリ菌の治療(除菌治療)
ピロリ菌感染がある場合には、抗生物質を内服することで除菌をすることができます。除菌の方法は以下のような薬剤を7日間内服することで行います、
一次除菌
プロトンポンプ阻害薬(PPIまたはカリウムイオン競合型アシッドブロッカー:P-CAB)+2種類の抗菌薬(クラリスロマイシン・アモキシシリン)を1週間内服。
約7割~8割の人で成功します。
二次除菌
一次除菌で効果がなかった場合、クラリスロマイシンを別の抗菌薬(メトロニダゾール)に変更し、再度1週間内服。
ピロリ菌除菌治療で気を付けて頂きたいこと
治療効果を高めるために、医師の指示通りに服薬することが大切です。3種類の薬を1日2回、1週間続けて飲むようにしてください。 自己判断で服薬を止めてしまうと、除菌ができないだけでなく、ピロリ菌に薬剤耐性がついてしまうこともありますので、注意が必要です。 また、2回目の治療を行う方は、飲酒を控えるようにしてください。
なお、1次除菌中も飲酒は控えて頂いた方が望ましいです。
ピロリ除菌治療の副作用
軽い下痢や柔らかい便などの消化器症状、味覚障害が起きた場合
自己判断で服薬量や回数を調整せずに、必ず1週間は服薬を続けるようにしましょう。 なお、症状が悪化した場合は、かかりつけ医や薬剤師までご相談ください。
発熱や腹痛を伴う下痢、粘膜や血液が混ざっている下痢、発疹の場合