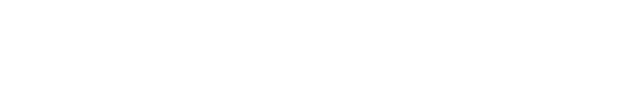逆流性食道炎
逆流性食道炎について
逆流性食道炎とは、強酸性の胃酸や消化液などの胃の内容物が食道に逆流し、食道粘膜に炎症を起こした状態を指します。食道粘膜は胃酸に対する防御機能が十分に備わっていないため、逆流が起こると容易にダメージを受けて炎症が生じます。
加齢に伴う食道の蠕動運動の低下、衣類による腹部の締め付け、長時間の前かがみ姿勢なども発症を助長すると言われています。市販薬で一時的に症状が改善することもありますが、逆流性食道炎は再発率が高い病気であるため、専門医による適切な治療と生活習慣の見直しが大切です。
逆流性食道炎の原因
ストレスや加齢、食の欧米化などがあげられます。
ストレスを受けると胃酸分泌が高まり、消化管の運動機能が落ちるため、逆流しやすくなります。
加齢に伴い、下部食道括約筋の働きが落ちたり、横隔膜の筋肉が弱くなることも原因となり得ます。腰が曲がり、前かがみになると腹圧が高まるため、症状が出やすくなります。
肥満も腹圧を上昇させ、妊娠・出産を契機に胃食道逆流症を発症される方もおられます。
食事内容に関して、脂肪分の多い食事は下部食道括約筋を緩め、胃食道逆流を誘発することが分かっています。
また、ピロリ菌は胃十二指腸潰瘍や胃がん発生のリスクを高めることが分かっているため、胃粘膜がピロリ菌に感染していることが分かれば、積極的に除菌治療が行われます。しかし、除菌されると胃酸分泌が回復するため、胃食道逆流症状はかえって増悪することがあります。
下部食道括約筋の機能低下
本来、胃酸の逆流を防ぐ弁の役割を持つ下部食道括約筋が緩むことで、胃の内容物が食道へ逆流しやすくなります。加齢や生活習慣、喫煙なども機能低下に関与します。
胃酸の過剰分泌
ストレスや暴飲暴食、香辛料やアルコール摂取によって胃酸分泌が増加すると、食道粘膜に強い刺激を与え、逆流性食道炎を悪化させます。
腹圧の上昇
肥満、妊娠、便秘、長時間の前かがみ姿勢などによってお腹の圧力が高まり、胃が押し上げられて逆流が起こりやすくなります。
食生活の影響
脂肪分の多い食事(揚げ物、チーズ、バターなど)は括約筋を緩め、逆流を助長します。コーヒー、炭酸飲料、チョコレート、香辛料なども症状を悪化させる原因です。
加齢や姿勢の変化
高齢になると食道の蠕動運動が弱まり、逆流した胃酸を押し戻す力が低下します。腰が曲がることで前かがみ姿勢になり、腹圧が上がりやすくなることも要因です。
ピロリ菌除菌後の影響
ピロリ菌除菌によって胃酸分泌が回復すると、逆流症状が出やすくなることがあります。除菌は胃がん予防には有効ですが、除菌後に胸やけが悪化するケースも見られます。
逆流性食道炎の症状
- 胸がムカムカする、胸焼け
- 食べ物が胸やのどにつかえる感じ
- 呑酸(酸っぱいものが上がってくる)
- げっぷの頻発
- 胃もたれ
- 慢性的な咳・ぜいぜいした息
- のどの違和感
逆流性食道炎の検査
逆流性食道炎の診断には、症状だけでなく検査による確認が必要です。特に胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)は最も有効で、逆流性食道炎の有無や重症度を正確に評価できます。
当院では最先端の内視鏡システムを使うことで時間をかけずに正確な検査を実現しています。また、鎮静剤の使用有無についても患者様のご希望に応じて選択可能です。
1. 上部消化管内視鏡(胃カメラ)
食道粘膜を直接観察し、炎症やびらん、潰瘍の有無を確認します。胃や十二指腸の病変(潰瘍・がんなど)も同時にチェックできるため、胸やけの原因が逆流性食道炎かどうかを見極めるのに有用です。
2. 24時間pHモニタリング
細い管を鼻から入れて、食道内の酸の逆流状態を24時間測定する検査です。逆流の頻度や強さを客観的に評価できます。胃カメラで炎症が見られない「非びらん性胃食道逆流症(NERD)」の診断にも役立ちます。
3.バリウム造影検査
バリウムを飲んでX線撮影を行い、食道と胃の形態や逆流の有無を確認します。簡便ですが、炎症の程度まではわからないため補助的に用いられます。
逆流性食道炎の治療
逆流性食道炎の治療は、大きく分けて 生活習慣の改善 と 薬による治療 が中心になります。軽症であれば生活の工夫だけで改善することもありますが、多くの場合は薬の助けが必要です。症状が長く続く場合や再発を繰り返す場合は、専門医の診察を受けることが大切です。
1. 生活習慣の改善(セルフケア)
逆流を防ぐために、日常生活でできる工夫があります。
-
食後すぐに横にならない(就寝は食後2~3時間あける)
-
就寝時に上体を少し高くして寝る(枕やベッドを調整)
-
脂っこい食事・刺激物を控える(揚げ物、チョコレート、コーヒー、アルコールなど)
-
適正体重を保つ(肥満は腹圧を高め、逆流を助長します)
-
禁煙する(ニコチンは食道の逆流防止機能を弱めます)
-
腹部を締め付けない服装を選ぶ
2. 薬による治療(薬物療法)
生活習慣を改善しても症状が続く場合、多くは薬での治療が行われます。
-
プロトンポンプ阻害薬(PPI)
胃酸の分泌を強力に抑える薬で、逆流性食道炎の第一選択薬です。数週間で症状が改善することが多く、再発予防にも使われます。 -
H2ブロッカー
胃酸分泌を抑える薬で、比較的軽症の場合やPPIが使えないときに用いられます。 -
制酸薬・粘膜保護薬
胃酸を一時的に中和したり、食道の粘膜を守る薬です。症状が軽い場合や補助的に使われます。