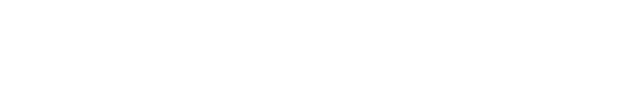機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシアとは
機能性ディスペプシア(FD:Functional Dyspepsia)とは、胃の痛みや胃もたれ、食後の膨満感などの症状が続くにもかかわらず、胃カメラなどの検査で潰瘍・炎症・がんなどの異常が見つからない状態をいいます。器質的な異常ではなく、胃の働き方(運動機能)や感じ方(知覚過敏)などの“機能的な異常”によって症状が起こると考えられています。
以前は「神経性胃炎」や「自律神経失調症」と診断されることが多かった症状の多くが、現在ではこの機能性ディスペプシアに分類されています。正式な疾患名としては2013年に確立され、現在では多くの医療機関で一般的な診断として扱われています。
慢性的な消化器症状でお悩みの中で検査を受けても、特に異常が発見されなかった方は、ぜひ当院へご相談ください。
機能性ディスペプシアの症状
主な症状
- 食後に胃が重い、少し食べただけですぐ満腹になる
- 胃のあたりが痛い、しくしくする
- 食欲がわかない
- 胃が張る、ガスがたまりやすい
- 吐き気や胸やけが続く
- 心窩部灼熱感(胸やけ)
症状の強さには個人差があり、ストレスや食生活、睡眠不足などによって悪化することもあります。
このような症状が慢性的に続き、食事に支障をきたすため、QOL(生活の質)低下を招いてしまいます。
機能性ディスペプシアの原因
機能性ディスペプシアの原因は一つではなく、胃の働き(運動)や感じ方(知覚)の異常、生活習慣、ストレスなど複数の要因が関係していると考えられています。それぞれの影響が重なり合って、胃の不快感や痛みなどの症状が起こるとされています。
胃の蠕動運動(動き)の低下
胃は食べ物を一時的にため、消化したあとに十二指腸へ送り出す働きをしています。この動き(蠕動運動)がうまくいかないと、食べ物の流れが滞り、胃もたれ・早期膨満感・吐き気などの症状が起こりやすくなります。また、胃の動きが弱まると十二指腸の働きにも影響し、胆汁の逆流によって不快感が強くなる場合もあります。
胃の知覚過敏
胃の粘膜が過敏になっている状態では、少量の食事でも強い痛みや圧迫感を感じやすくなります。これは胃の神経が過剰に反応してしまうことが原因と考えられています。
生活習慣・食生活
不規則な生活、睡眠不足、過労、ストレスのほか、以下のような習慣が症状を悪化させることがあります。
- タバコ、アルコール、コーヒーなどの嗜好品
- 脂っこい食事や刺激の強い香辛料
- 早食いや過食
- 食事時間の乱れ
ストレスや自律神経の乱れ
胃の働きは自律神経によって調整されています。ストレスや精神的緊張によって自律神経のバランスが乱れると、胃の動きが低下したり、胃酸分泌が不安定になり、症状が悪化することがあります。
ヘリコバクター・ピロリ菌の感染
ヘリコバクター・ピロリ菌に感染すると、慢性胃炎を起こし、胃粘膜が敏感になることがあります。除菌後に症状が改善するケースもありますが、機能性ディスペプシアとの関係は個人差が大きいとされています。
機能性ディスペプシアの検査・診断
機能性ディスペプシアは、胃や食道、十二指腸などに明らかな病変がないにもかかわらず、胃の不快感や痛みなどの症状が続く状態です。そのため、まずは同じような症状を起こす他の病気(胃潰瘍・胃がん・逆流性食道炎など)がないかを確認するための検査を行い、器質的疾患を除外したうえで最終的に診断されます。
胃カメラ検査(上部消化管内視鏡)
最も重要な検査です。口または鼻から細いスコープを挿入し、食道・胃・十二指腸の粘膜の状態を直接観察します。炎症や潰瘍、がんなどの病変がないかを確認し、必要に応じて組織を採取(生検)して詳しく調べます。また、採取した組織でピロリ菌感染の有無を調べることも可能です。
当院では、最新の内視鏡システムを導入し、苦痛を最小限に抑えた検査を心がけています。内視鏡専門医が丁寧に対応いたしますので、検査が初めての方も安心してご相談ください。
腹部エコー(腹部超音波検査)
胃以外の臓器が関係している場合もあるため、肝臓・胆のう・膵臓・腸などの周辺臓器の状態を調べます。腹部の痛みや不快感が続く場合、胃以外の原因(胆石や膵炎など)を見逃さないために有効です。痛みのない検査で、体への負担もほとんどありません。
機能性ディスペプシアの治療
機能性ディスペプシアは、症状の出方や原因が人によって異なるため、一人ひとりに合わせた治療を行うことが大切です。基本的には、生活習慣の見直し(生活指導) と 薬による治療(薬物療法) を組み合わせて行います。
生活習慣・食生活の改善
胃の働きは自律神経によってコントロールされているため、生活リズムの乱れやストレスが症状を悪化させることがあります。日常生活の中でできることを意識して、少しずつ整えていきましょう。
主なポイント
- 規則正しい生活を心がける
- 食事は少量ずつ、ゆっくりとよく噛んで食べる
- 食後すぐに横にならない
- 睡眠不足や過労を避ける
- ストレスを溜めすぎないようにする(趣味やリラックス時間を持つ)
控えたほうがよいもの
脂っこい食事、甘いもの、刺激の強い香辛料、柑橘類、カフェイン飲料(コーヒー・紅茶・抹茶など)、アルコール、喫煙
生活を少しずつ整えることで、症状が和らぎ再発を防ぐことにもつながります。
薬物療法
症状の内容や原因に合わせて、薬を組み合わせて使用します。
- 胃酸分泌抑制薬(PPI、H2ブロッカーなど)
胃酸の出過ぎを抑え、胃の粘膜を保護します。 - 消化管運動改善薬(アコチアミドなど)
胃の動きを整え、もたれ感や膨満感を改善します。 - 抗不安薬・抗うつ薬
自律神経のバランスを整える目的で、ストレス性の症状が強い場合に使用されることがあります。 - 漢方薬
体質や症状に合わせて処方し、胃の機能を穏やかに調整します。 - ピロリ菌陽性の場合
感染が確認された場合は、除菌治療を行うことで症状が改善することがあります。
薬の効果には個人差があるため、医師と相談しながら、体調に合わせて治療方針を調整していきます。