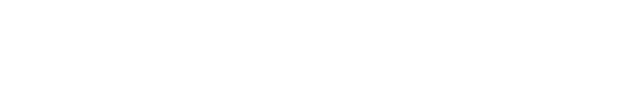食道がん
食道がんとは
食道は、のどから胃へとつながる管状の臓器で、口から摂取した飲食物を胃に送り届ける役割を担っています。 食道の内側を覆う粘膜の上皮に発生する悪性腫瘍を「食道がん」と呼びます。
食道がんは、進行すると粘膜下層や筋層へと浸潤し、さらに周囲の臓器(肺・気管・大動脈など)に広がることがあります。また、食道周囲には血管やリンパ管が密集しているため、そこを通じてリンパ節転移や遠隔転移をきたすことも少なくありません。
日本では男性に多く、男女比はおよそ6:1。発症は40代後半から増え始め、70代でピークを迎えるとされています。特に「お酒を飲むと顔が赤くなる体質の方」は、食道がんのリスクが高いことが知られています。
食道がんの種類
食道がんは大きく扁平上皮がんと腺がんに分けられます。
| 扁平上皮がん | 日本人の食道がんの約9割を占めます。主に喫煙や飲酒と強い関連があり、また熱い飲み物の摂取もリスク因子とされています。 |
|---|---|
| 腺がん | 欧米で増加しているタイプで、日本でも徐々に増加傾向にあります。逆流性食道炎やバレット食道など、胃酸の逆流による慢性炎症と深く関連しており、肥満や脂肪分の多い食生活もリスク要因とされています。 |
食道がんの症状
早期の食道がんはほとんど症状が出ないため、健診や内視鏡検査で偶然発見されることがあります。進行すると以下の症状が出てきます。
- 食べ物がつかえる感じ(嚥下障害)
- 胸の痛みや違和感
- 体重減少
- 声のかすれ(反回神経への浸潤による)
- 咳や誤嚥(気管への浸潤による)
食道がんの検査
胃カメラ検査やバリウムによる造影検査によって確定診断を行います。 疑わしい病変が見つかれば、組織採取を行い生検に回すことも可能です。
また、MRI、CT、PET検査といった画像検査によって、がんの進行状態や転移の有無などをチェックし、病期の判定を実施します。
食道がんの治療
食道がんの治療には、内視鏡治療、外科手術、放射線療法、化学療法などがあります。どの治療を行うかは、がんの進行度や患者さんの体力、全身の状態などを考慮したうえで、主治医が最適な方法を判断します。
早期の段階で発見された場合は、体への負担が少ない内視鏡治療で対応できることもあります。進行している場合は、手術や放射線治療、抗がん剤を組み合わせる治療(集学的治療)が行われることもあります。
食道がんの予防と早期発見
食道がんは生活習慣病的ながんであり、以下の対策でリスクを減らすことができます。
- 禁煙・節酒
- 野菜や果物をバランスよく摂取
- 熱すぎる飲食を避ける
- 逆流性食道炎やバレット食道の定期的な検査
特に、早期の食道がんは内視鏡で治療可能ですが、進行すると治療が難しくなるため、定期的な胃カメラ検査による早期発見が重要です。